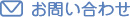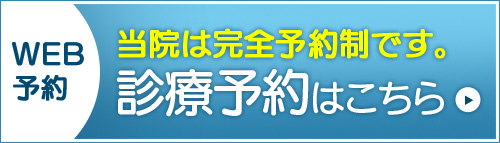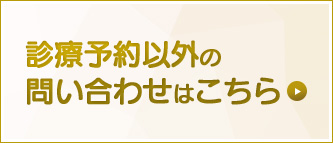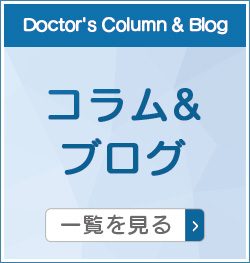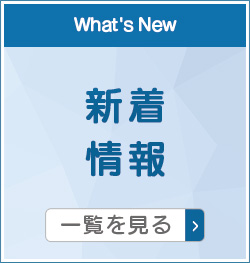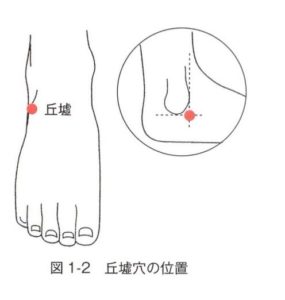内分泌・代謝・栄養の病気
テーマ:高プロラクチン血症は医原病か?
若い女性の原因不明の無月経の約20%が、高プロラクチン血症によるものだといわれています。
原因は、私ども内科医や精神科医あるいは婦人科医等の処方薬の副作用によるものが多いです。
概念:
プロラクチン産生下垂体腫瘍(プロラクチノーマ)は、脳下垂体の腫瘍の一つで、
プロラクチンというホルモンを産生し、高プロラクチン血症を来たし、
無月経乳汁漏症候群を来たします。
生理:
プロラクチンに限らず、生体内にはホルモン分泌量を制御する仕組みがあります。
妊娠・授乳行為⇒プロラクチン分泌↑⇒LH(黄体化ホルモン)↓・
FSH(卵胞刺激ホルモン)⇒(中枢性)性腺機能(ゴナドトロピン)↓
⇒無月経・不妊
原因:
Ⅰ.抗ドパミン作用を有する向精神病薬:
①三環系抗うつ薬(アミトリプチリン、イミプラミン)
②抗精神病薬ブチロフェノン系(ハロペリドール)
③フェノチアジン系(クロルプロマジン、ベルフェナジン)
Ⅱ.抗ドパミン作用を有する消化器系薬剤:
①制吐剤(メトクロプラミド、スルピリド、ドンペリドン)は
ドパミン受容体を遮断するため、プロラクチン分泌も亢進します。
②H2受容体拮抗薬(シメチジン、ラニチジン)
Ⅲ.中枢ドパミン系に影響を与える降圧剤(α-メチルドパ、レセルピン)
Ⅳ.経口避妊薬(エストロゲン製剤)
原発性甲状腺機能低下症では、視床下部からのTRH分泌が上昇する結果、
プロラクチン分泌も亢進します。
症状:
高プロラクチン血症が女性に見られた場合、無月経、乳汁漏出、
不妊等を伴い無月経乳汁漏症候群としてしられています。
男性では自覚症状が出現しにくく、勃起不全などが出現しても
申告しにくい症状であるためか発見が遅れがちです。
下垂体性の高プロラクチン血症では、しばしば視野狭窄がみられます。
分娩後、長期間の授乳によりプロラクチンの分泌が亢進し、
ゴナドトロピン分泌が低下することによって生じる高プロラクチン血症は
キアリ・フロンメル症候群と呼ばれますが、
分娩と関係ないものではアルゴンツ・デル・カスティージョ症候群と呼ばれてきましたが、
いずれも微小な下垂体腫瘍の存在が否定できないことがあるため、
無月経乳汁漏症候群に括られるようになりました。
検査:
① 血中プロラクチン値を複数回測定して、いずれも≧20ng/mL
とくに100ng/mLを超える場合にはプロラクチン産生腫瘍の可能性を考えます。
②画像検査:MRIで下垂体および下垂体茎・鞍上部の病変を見つけます。
治療:
他の下垂体腫瘍と比較して特徴的なのは、
薬物療法が有効なので手術療法より優先されることです。
#1.持続性高プロラクチン血症の治療
1-1:薬剤によるものであれば、原因薬物の中止・変更をします。
1-2:原発性甲状腺機能低下症、先端肥大症、下垂体茎・鞍上部病変など、
他疾患に伴うものは原疾患の治療をします。
#2.プロラクチノーマの治療
2-1:薬物療法はドパミン作動薬が第一選択です。
高プロラクチン血症では、原因と背景状況によって治療法が異なり、
妊娠や薬剤性のものでは、ブロモクリプチンを使わないこともあります。
ただし、産褥期の多くの高プロラクチン血症による母乳分泌抑制に用いられるのは
ブロモクリプチンです。
第一選択薬となるドーパミンD2受容体作動薬(ブロモクリプチン、テルグリドなど)には、
強力なプロラクチン分泌抑制作用があり、
血清プロラクチン値の正常化、腫瘍縮小効果は70%以上です。
ただし、副作用として消化器症状(嘔気・嘔吐)、起立性低血圧などが多いため、
服薬中止例が多く、薬剤中止によるプロラクチン値の再上昇、腫瘍の再増大が問題となります。
そこで、他の第一選択としては長時間作用型の選択的ドーパミン作動薬
(カベルゴリン)が用いられます。
この薬剤は、週一回の低用量服薬で済み、寛解率も高く、
消化器症状などの副作用が少ないです。
この薬剤は、従来、パーキンソン病に使用されていましたが、
高用量では炎症性線維化反応により心臓弁膜症を起こすことが問題視されていました。
2-2:手術では薬物療法が無効な場合、
巨大な腫瘍による腫瘍圧迫症状(視力障碍など)が認められる場合、
将来挙児を希望する場合は、手術(経蝶形骨洞下垂体摘出手術:Hardy法)も検討されます。
2-3:放射線治療としてガンマナイフ、サイバーナイフがあります。
薬物治療無効例で手術で全摘できなかった症例、
再発した増殖性の高い腫瘍などを対象にします。
ただし、有効率は低く、下垂体前葉機能低下症をもたらすことがあるため、
必ずしも血清プロラクチン値の低下を目的として行う必要はありません。