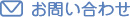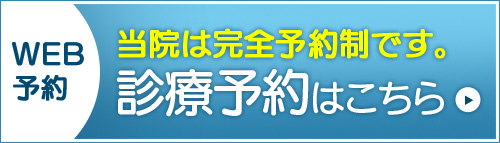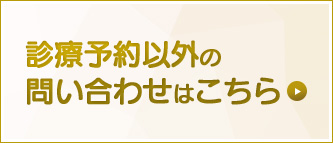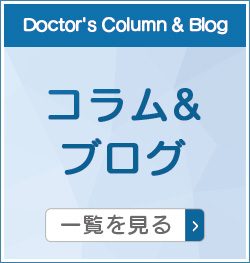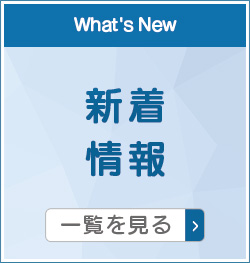心療内科についてのQ&Aをご紹介いたします。
それは日本心療内科学会のHPです。
心療内科Q&Aのコラムを読むことができます。
Q&Aは、想定した事例です。Q&Aや疾患についてのご質問、病院の紹介等は、受け付けておりませんのでご了承下さい。※「質問」をクリックする、が表示されます。
と書かれています。
高円寺南診療所に通院中の皆様が、一般論であるこのQ&Aを読んでいただくためには、実際に即した具体的な解説が必要だと考えました。
そこで、「質問」「答え」の後に、
<高円寺南診療所の見解>でコメントを加えることにしました。
「質問10」
息子が、適応障害という診断を会社の健康管理センターで受けました。
本人は身体疾患の不調を主に訴えていますが、心療内科と精神科ではどちらの科を受診すればよいでしょうか?
「答え」
一般的に学業や職業、家庭生活といった日常生活上の適応に失敗したケースを適応障害と呼びます。
ご子息の場合はおそらくは仕事上の様々なストレス因子に心身が反応して、身体の不調を自覚されたものと推察されます。
適応障害は、不安や抑うつといった精神症状として表れる場合もあり、その際は精神科受診が適していると言えます。
しかしながら、ご子息の場合は、ご自身の不調を身体疾患として自覚されているので、この場合は心療内科への受診が望ましいでしょう。
心療内科では、まず身体的に必要な検査を行い、ご本人の症状を説明できるような身体疾患の有無を調べます。
それと同時に、それまでの経過やこれまでの身体症状に対するご自身の反応などについて詳しくお聴きして、ご子息が職場等でどのようなストレッサーに晒されていて、それに今回どう反応されたかについてご本人と共に確認します。
もし、身体疾患が存在していれば、その治療を行うと同時に、例えば職場でのストレッサーに今後どのように対応して行けばよいかを、医師やあるいは心理士を交えて検討して行きます。
一般的なストレス発散法や、緊張が強いときなどには自律訓練法などのリラックス法を修得していただくこともあります。
さらに、ご本人の対人関係の持ち方に何か問題があれば、それを修正してストレス状況を産み出さないような接し方を心がけていただきます。
また、不安や抑うつが身体症状の発現や経過に関係していると推察される場合においては、必要に応じて抗不安薬や抗うつ薬を処方することもあります。
これらの対応をした後に身体症状が改善して行けば、症状発生前のストレッサーが症状と関係していたことを更に認識することが可能となり、ご本人のその後の適応行動にも大きな示唆が得られることが期待されます。
このように心療内科は心身両面を同時に評価し、共に修正して行こうとする診療科ですので、身体疾患を訴えられる適応障害には最も適した診療科ということができます。
(岡田宏基)
<高円寺南診療所の見解>
岡田宏基(おかだひろき)先生は、香川大学の医学教育学の教授です。岡山大学医学部医学科をご卒業後、医学博士号は香川医科大学(現、香川大学医学部)で取得されたようです。
岡田先生の解説は、高円寺南診療所のような、心療内科専門医が在籍している医療機関で実施している診療内容を解り易く解説してくださっています。そのため、新たに付け加えることはありません。
ところで岡田先生は、香川大学医学部付属病院総合内科に所属する日本心療内科学会の登録指導医・専門医ですが、四国では唯一の心療内科専門医です。徳島、愛媛、高知には不在です。このように執筆者のプロフィールと背景をなぜ詳細にご紹介するのかというと、それには大切な理由があるからです。
まず、「質問10」の相談者は、ご自分の息子さんを心配されています。
<心療内科と精神科ではどちらの科を受診すればよいでしょうか?>という相談者の問いに対して、岡田先生は<ご子息の場合は、ご自身の不調を身体疾患として自覚されているので、この場合は心療内科への受診が望ましいでしょう。>と回答されています。
しかし、このご回答は残念ながら適切ではないと思います。
相談者の息子さんの生活空間が全国の主要都市もしくはその近郊であれば、心療内科へのアクセスは容易ですが、たとえば、四国在住であれば、岡田先生を受診するしかないことになるからです。
精神科医のほとんどが心療内科を標榜している現状において、心療内科専門医不在地域の患者さんに対して心療内科受診を勧めるということは、精神科受診をすすめているのと実質的にはかわりありません。
ましてや適応障害を疑われている状態では、心療内科を標榜する一般内科医をすすめることは論外であると思われます。
もし、私(飯嶋正広)が回答者であれば、上記のようなケースにおいては、かかりつけ医もしくは一般内科・総合内科の受診を勧め、身体疾患の有無をチェックした上で、精神科受診を検討していただくようアドバイスします。
内科医と精神科医との連携による診療が受けられるようにするアプローチが現実的だと思います。
岡田先生は香川大学付属病院の総合内科に所属されているのだから、そのあたりを遠慮せずにアピールしていただく手はなかったのか、残念です。
最近、<総合医>とか<総合診療>とかが叫ばれていますが、私は楽観的にみてはいません。なぜなら、心療内科専門医こそが総合医・総合診療医の担い手として最も適任であるはずなのに、その肝心な心療内科専門医の絶対数が不足し、しかも偏在しているからです。
しかし、逆に言えば、質の高い内科専門医を育成していけば、将来、有能な総合医・総合診療医が活躍できることになり、「質問10」の相談者のような悩みは減るのではないかと考えます。
日本心療内科学会のホームページでのQ&Aであるために、学会の立場からの解説が多いことが残念です。
解説はあくまでも学会や、執筆者ご自身の立場のためであってはならず、相談者の立場に立ち、現状を踏まえた現実的で有益な解説をしていただきたいものです。
ARCHIVE
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月