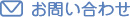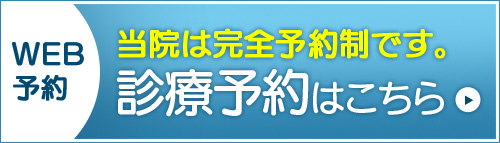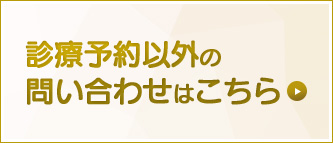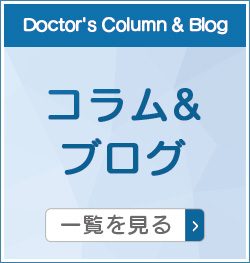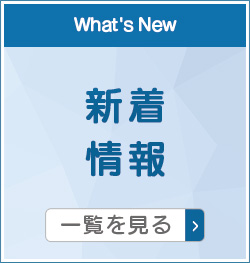懸垂理論から学ぶNo4
懸垂のパラドックス<結論>時間をかける
簡単な運動ですが、正しく行うには時間と努力が必要です。
文責:クリスティ・アシュワンデン
The Pull-up paradox
It’sa simple exercise,but getting it right takes time and efforts
By Christie Aschwanden
水氣道の稽古を続けていくうえで学ぶべきエッセンスは、懸垂のような一見シンプルな競技ほど豊かです。
時間をかけること、辛抱すること、トレーニングの一貫性を保つこと、周期的に継続すること、目的とするパフォーマンスを習得するためには、その手段としての準備的なエクササイズを用いること、生まれつき有利な人と不利な人や向き不向きはあるがトップアスリートを目指すのでなければ努力と工夫で達成できること、など。
そうして得られるものは、より強くなれること、達成の暁には大きな満足感が得られること、スーパーヒーローになったような気分になれること、他の動きや技も軽々と行えるようになること、など・・・
懸垂や重量挙げには、身長や体重、腕の長さや筋力、体形などによって向き不向きがあり、かなりの根気や辛抱が求められるようです。また孤独に打ち勝たなければなりません。
これに対して、水氣道には、ほとんど向き不向きはありません。老若男女が同じ土俵(プール)で一緒に楽しく稽古できることが水氣道の素晴らしさであることを改めて感じさせられます。団体での生涯エクササイズは、自然で健康的な世代間交流の場を提供しています。
<結論>時間をかける
「辛抱してください」とキングさん。一晩でできることではありません。
一貫性が重要だと彼女は言う。
「これは避けて通れない道です。毎週、毎月、取り組まなければならないのです。
健康科学ライターで、ウェイトリフティングのガイドブック「Liftoff」の著者であるケイシー・ジョンストンにとって、これは重要なことです。健康科学ライターで、重量挙げのガイドブック『Liftoff: Couch to Barbell』の著者であるケイシー・ジョンストンにとって、懸垂はより強くなるための大きな探求の一部にすぎませんでした。
懸垂ができるようになるまでには、1年ほど重量挙げを続けていましたが、その甲斐あって達成感を味わうことができました。「懸垂をする必要はないんです。「私は腕が長く、そして、比較的体が大きく、その両方ともが難題です。」
確かに、懸垂が簡単にできる人とそうでない人がいるのは事実です。
「一般に、体重が増えるほど、体重に対する強度の比率は下がる」とは、StrongerBySceience.comの創設者で、3つの世界記録を持つパワーリフト競技者のGreg Nucklosの述懐です。背の高い人は、同じような体格であっても、背の低い人よりも引き上げる質量が多くなる可能性が高いのです。
手足が長い私が懸垂の記録を出すことはないだろう。しかし、私にはいくつかの有利な点がある。
クロスカントリースキーで鍛えた上半身の強さと、中年体型でないことだ。 懸垂はまだまだ努力が必要だが、その分、満足感も大きい。
「鉄棒、塀の上、壁の上など、何かに向かって体を引き上げると、スーパーヒーローになったような気分になります」とキャラウェイさんは言います。それだけでなく、近くの遊び場の鉄棒も少し楽しくなります。
以下、 原文
TAKE YOUR TIME
“Be patient,” Ms.King said. Your first pull-up “takes time and a lot of consintency; it doesn’t happen overnight.”
Consistency is important, she said.
“There is no way around this. You have to work at it, week after week and month after month.”
For Casey Johnston, a health and science writer, and author of the weight lifting guide “Liftoff: Couch to Barbell,” pull-ups were just one part of a larger quest to get stronger. She’d been weight lifting for about a year before she could finally do one, but it was worth it for the sense of accomplishment. “No one is required to do pull-ups,” she said. “I have long arms and I’m relatively big, which are both challenges.”
It’s true that pull-ups are easier for some people than for others. “ In general, as mass goes up, strength to weight ratios go down,” said Greg Nucklos, founder of StrongerBySceience.com and a powerlifter who’s held three world records. A tall person is likely to have more mass to pull up than a shorter person, even if they are similarly built.
I will never set any pull-up records with my long arms and legs. But I do have a few advantages:
Good upperbody strength from years of cross-country skiing and not too much middle-aged pudge. I still have to work at pull-ups, but the payoff is deeply satisfying.
“Pulling yourself up onto something- a bar, over a fence, up a wall- makes you feel like a superhero,” Ms.Callaway said. Not only that, she added, it also makes the monkey bars at the nearby playground a little more fun.