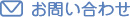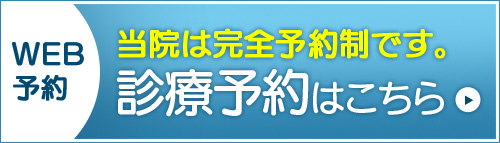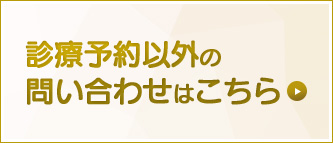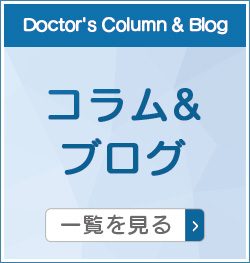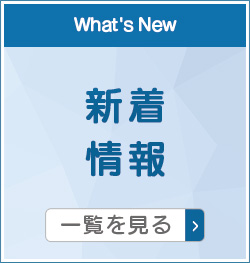心療内科についてのQ&Aをご紹介いたします。
心療内科Q&Aのコラムを読むことができます。
Q&Aは、想定した事例です。Q&Aや疾患についてのご質問、病院の紹介等は、受け付けておりませんのでご了承下さい。※「質問」をクリックするとが表示されます。
と書かれています。
高円寺南診療所に通院中の皆様が、一般論であるこのQ&Aを読んでいただくためには、実際に即した具体的な解説が必要だと考えました。そこで、「質問」「答え」の後に、
<高円寺南診療所の見解>でコメントを加えることにしました。
Q
心療内科で心の病気を診ていただけるのはどのような場合でしょうか。
また、心療内科でしていただける心理療法には、どのようなものがありますか?
A
心身症とは、病気の発症や経過にストレス等の心理社会的な因子が密接に関係し、器質的な障害(例:潰瘍のような、組織の病変)や機能的障害(例:血圧コントロールのような、身体機能の調節の障害)が認められる身体の病気を指しています
(日本心身医学会教育研修委員会、1991)。
つまり、ストレスや人間関係といった心理社会的な要因が身体の病気の変化に大きな影響を及ぼしており、その治療にあたっても心理社会的要因を考慮しなければならない病気です。
ですから、心療内科は「心の病気」を診るというよりも、「心が影響している身体の病気」、つまり、心身症を専門的に見る医療機関だと言えるでしょう。
一方、うつ病などの精神疾患の患者さんもさまざまな身体の症状を訴えますが、精神疾患に伴う身体の症状は心身症とは考えません。
「心の病気」と呼ばれる状態が、精神疾患を指しているとすると、それらの治療は精神科が専門に行うことになります。
ただし、「精神科」と「心療内科」の両方を同時に看板に掲げている場合には、精神疾患だけではなく、心身症の治療も行っているところがあると思われます。
身体の病気に影響しているストレスや人間関係等の心理社会的要因を明らかにして、それらに働きかけていこうとする治療法は「心身医学療法」と呼ばれていますが、自律訓練法、行動療法・認知行動療法、交流分析という3つの治療法は、心身症治療の基本的な専門的治療法と呼ばれています。
また、心理社会的要因の改善を図るためには、治療者と患者さんの良好な治療関係が前提となりますが、心療内科の専門家(医師、心理士他)は、患者さんの訴えをじっくりと聞くことのできる態度や環境への配慮といったカウンセリングの基本を身につけています。
この他、森田療法、バイオフィードバック療法、絶食療法といったより専門的な心身医学療法もあります。どのような場合に適用されるかは、心療内科でご確認ください。
(坂野雄二)
<参考文献>
日本心身医学会教育研修委員会(編)「心身医学の新しい診療指針」1991
<高円寺南診療所の見解>
この質問と全く同じ質問を受けることは、実際にはほとんどありません。
しかし、類似した内容の質問は数多く受けます。むしろこうした質問をためらい疑問を募らせながら心療内科を受診している方が多いのではないかと思います。
回答者の坂野 雄二(さかの ゆうじ、1951年 - )先生は、教育学博士(筑波大学)であり、認知行動療法を専門とする臨床心理士です。
すでに退官されたようですが、北海道医療大学教授を勤めておられました。そうした心のケアの専門家の立場からの回答には私自身も大いに興味があり、参考になります。
坂野先生の説明の通り、心療内科は「心の病気」を診るというよりも、「心が影響している身体の病気」、つまり、心身症を専門的に見る医療機関です。
また、坂野先生の説明には一工夫がなされています。
<「精神科」と「心療内科」の両方を同時に看板に掲げている場合には、精神疾患だけではなく、心身症の治療も行っているところがあると思われます。>
逆に言えば「精神科」と「心療内科」の両方を同時に看板に掲げている場合には、もっぱら精神疾患しか診ず、心身症の治療を行っていないにもかかわらず「心療内科」の看板を掲げているところがある、ということ暗示しています。
実際には、「心療内科」を同時に標榜していない生粋の「精神科」はとても少ないのが現状です。
心身症に対して「心身医学療法」を駆使して診療に当たるのが心療内科専門医です。
そして心身医学療法の専門家とは、心療内科専門医や心身医学療法に習熟した臨床心理士等を指し、たしかに<患者さんの訴えをじっくりと聞くこと>のできる態度や環境への配慮といったカウンセリングの基本を身につけています。
しかし、心療内科専門医はカウンセラーではないので、患者さんの訴えを<じっくりと聞くこと>とは、時間的な長さの問題ではなく、質的な深さを意味するものとご理解いただいた方が現実的でしょう。
時間をかけた本格的なカウンセリングは、専門の臨床心理士等が担当するのが妥当だと思います。逆に、
臨床心理士とは、たとえ心身医学療法の専門科であって、心療内科専門医をリーダーとする心療内科チームに属している場合であっても、心療内科の専門家を称するべきではありません。
なぜならば、心療内科も医学の中核である内科の一部門だからです。また心療内科専門医が不在で心理士のみのチームであればなおのことです。この点に関しては、残念ながら坂野先生のご説明不足のように思われます。
心身医学療法には、心身症の治療のために確立した多くの手法がありますが、さらなる工夫と研究開発が望まれます。
そのため高円寺南診療所もオリジナルの心身医学療法を開発し、実践を重ね、実績を挙げているのが、水氣道と聖楽療法です。
この二つは、単なる心身医学療法を超えて『全人療法』に向かって発展を続けている『全人的療法』です。これらの全人的療法は狭い意味での心身症のみならず、ストレスの影響を強く受ける多くの一般的な病気である生活習慣病や心のメンテナンスにも威力を発揮し、難病視されている線維筋痛症などにも顕著な効果をみせています。
ARCHIVE
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月