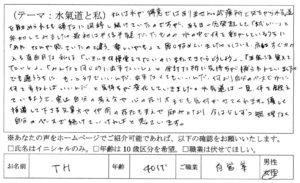総合リウマチ科(膠原病、腎臓、運動器の病気を含む)
<リウマチ結節、痛風結節、それとも石灰化上皮腫?>
リウマチ科では、しばしば皮下腫瘍や結節と遭遇することがあります。
そこで役立つのが超音波検査です。とくに関節リウマチでは、表在超音波による関節滑膜の観察は日常的な検査項目になってきました。
最近では体表部の病変の診断に表在エコー検査は、甲状腺や唾液腺、耳下腺や皮膚科・形成外科領域の表在腫瘤の有無や周囲のリンパ節の腫れを調べます。
また、血流ドプラー法を併用すれば、炎症の程度や拡がり、あるいは悪性腫瘍に特徴的な異常血流パターンの有無を確認できます。
さらに悪性が疑われる腫瘤をエコーで確認しながら針を刺し、エコー下穿刺吸引細胞診をおこなって、採取した細胞を顕微鏡で観察してより精度の高い検査を行うことがあります。
ようやく先々週の水曜日、11月1日に東京警察病院形成外科を受診し、事前の血液検査を済ませて、8日に手術による腫瘍摘出、15日に抜糸処置および摘出腫瘍の病理診断報告を得て終了となりました。
縫合技術は一般外科の水準とは異なり、芸術的でありました。
形成外科は美容外科を兼ねることが多いのでそのためかもしれませんが、お見事であります。
さて病理の結果は、石灰化上皮腫といって、中高年者ではなく、子供に多い腫瘍ということで、一つ勉強になりました。
水氣道を創始して、継続的に鍛錬している人体に発生する腫瘍とは、いかなる腫瘍か、自分自身を第三者の立場から観察し、考察していましたが、何となく納得できてしまう結果であったように思います。
つまり、私は一昨日で58歳になりましたが、まだまだ成長期の肉体を持っているということです(医学的根拠はありませんが!)
最近では体表部の病変の診断に表在エコー検査は、甲状腺や唾液腺、耳下腺や皮膚科・形成外科領域の表在腫瘤の有無や周囲のリンパ節の腫れを調べます。
また、血流ドプラー法を併用すれば、炎症の程度や拡がり、あるいは悪性腫瘍に特徴的な異常血流パターンの有無を確認できます。
さらに悪性が疑われる腫瘤をエコーで確認しながら針を刺し、エコー下穿刺吸引細胞診をおこなって、採取した細胞を顕微鏡で観察してより精度の高い検査を行うことがあります。
そこで、日本形成外科学会のHPを検索してみたところ、石灰化上皮腫について、一般の患者さん(あるいはその家族)にもわかりやすい言葉で説明してありました。
このような文体で表現することは、なかなかの技術を要します。
私の文体は、硬く、重く、難解になる傾向があるので、大いに参考にさせていただこうと思います。
ただ、私が知りたかったのは、石灰化上皮腫に対する形成外科学会での検査体系についてです。
検索してみると、レントゲン、CT、MRIなどは紹介されていますが、超音波検査の有用性については触れられていませんでしたので、一般にはまだ余り普及していない可能性があるのではと推定しました。
もっとも、警察病院でお世話になったDr.平井は触診のみで石灰化上皮腫を見抜いておられたのでさすがであります。
一般社団法人日本形成外科学会のHPより引用
ただし、下線や太字は飯嶋正広が加工しました。
一般社団法人日本形成外科学会HP
1.疾患の解説
どのような病気か?
石灰化上皮腫とはその名の通り皮膚の一部が石灰のように硬くなる良性の皮下腫瘍の一つです。
他の皮膚皮下腫瘍と同じようになぜ発生するのか原因は分かっていませんが、毛母腫(pilomatorixoma)という別名が現すように毛根に存在する毛母細胞を起源とする腫瘍です。
比較的若い人、特に小児の顔(まぶた)、腕、頸などに発生することが多いようです。
症状は?
臨床的には皮膚の直下に石の様に硬いしこりを触れます。
殆どの場合無症状ですが、時に痒みや圧痛(押すと痛い)を感じることもあります。
皮膚の色は正常か、または腫瘍の上の皮膚が薄い場合は下の腫瘍が透けて見えて黄白色や青黒い色に見えることもあります。
触ると表面は凸凹していますが、境界は明瞭で可動性は良好です。
一般的に悪性腫瘍(癌や肉腫)は硬く、表面が凸凹していることが多いのですが、悪性腫瘍は表面から触って腫瘍を動かそうとしても殆ど動かないことが多いのに対してこの腫瘍は皮膚の下で移動するという違いがあります。
ただ大きなものや、可動性が悪いもの、皮膚表面が破裂してしまったものなどでは、時として悪性腫瘍と見分けがつかないこともあります。
どうやって診断するか?
診断はまず臨床的に上記のような臨床症状からある程度判断することができます。
ただし粉瘤、ガングリオン、類皮嚢腫など他の皮膚皮下良性腫瘍と見分けがつかない場合もあります。
レントゲン撮影をして石灰化を確認することにより、更に診断の確度は高まります。
ただし、石灰化の程度は様々なので、石灰化が進行していない場合レントゲンで映し出されない場合もあります。
また部位によってはCTやMRIで周辺臓器との位置関係を事前に確認しておかなければならない場合もあります。
2.治療法
この腫瘍の成長はゆっくりですが、自然に治ってしまうことはありません。
また飲み薬や付け薬、レーザーなどで腫瘍をなくすこともできません。
細菌感染を起こせば赤くはれ上がります。
また既に述べたように悪性腫瘍との鑑別が必要な場合もありますので、原則的には外科的に手術をすることが望ましいと考えられています。
そして手術で摘出した組織を顕微鏡で見る検査(病理学的検査)することによって確定診断をします。
摘出術は、年齢と腫瘍の大きさにもよりますが、小学校高学年以上であれば殆どの場合局所麻酔で日帰り手術が可能です。
年少児の場合や大きなものの場合には全身麻酔が必要です。
傷痕に関しても形成外科的な手技を用いることでかなり目立たない傷痕にすることができます。
(中にはケロイド体質といってどんなに傷を丁寧に縫合しても傷痕が赤く盛り上がってしまう方もいますが、その場合は術後更にケロイドの治療が必要になります。)
3.治療により期待される結果
手術することによって治癒が期待できます。
腫瘍自体がもろいので、完全摘出できなかった場合再発する場合もないわけではありませんが、その場合も再手術で根治が期待できます。
本腫瘍が転移したり、本腫瘍が直接の原因で生命を脅かすことはありません。